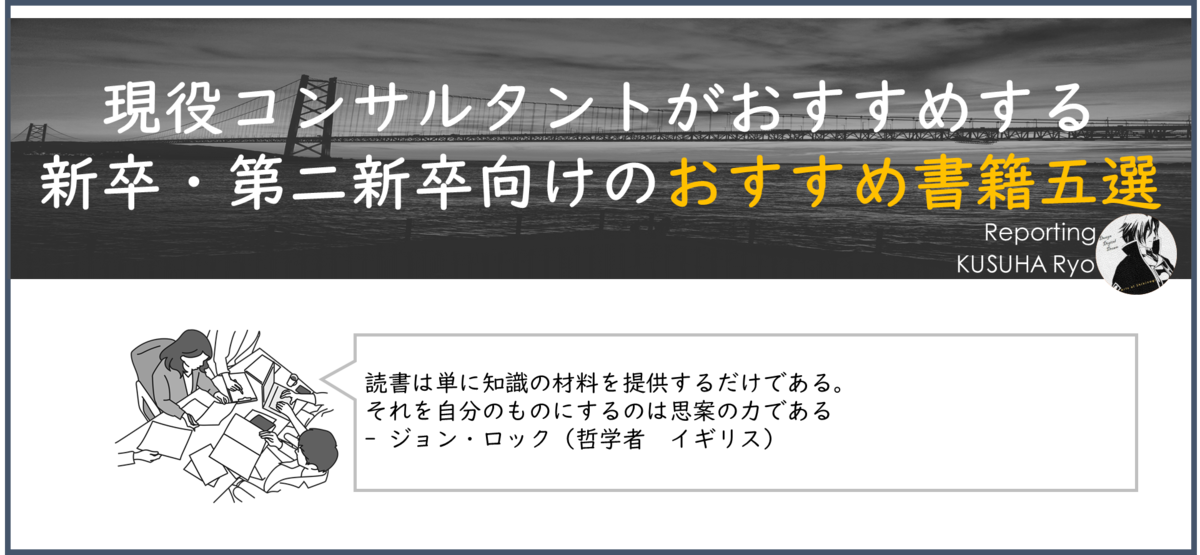
※Amazonアフィリエイトでは自分へのご褒美に梅干しや塩昆布、それからおいしいおにぎりを買おうと思っていますので、よければ。。参考文献などをぽちっといただけますと。
コンサルティング業務において、書籍の知識は必要に応じて、あるいは予め備えておくものです。
例えばアパレル業界や化粧品業界のリブランディングプロジェクトにあなたが木曜日や金曜日にアサインされたとして、翌週月曜日からプロジェクトが開始される場合にはまだ時間があります。
その際に、必要最低限の業界知識や対象企業の売り上げ規模、ブランド概要が頭に入っていないと、会話がそもそもつながらないということもざらにあります。
コンサルタントとして必要な力はおおよそ5つ。本記事では、調べる力にフォーカスします。
②描く力・・構想をまとめ上げる力や、解くべき課題の切り口をみつける力
③導く力・・部下、クライアント問わず関係者を自然な形で、あるいは時にあえて強引な形で誘導する力
④話す力・・相手によって、緩急をつけた話し方と、適切な粒度での話ができる力
⑤調べる力・・デスクトップリサーチの勘所、ヒアリングの進め方
⑥参考書籍について 【本記事】
1. どういう観点でコンサルタントとしての基礎を学ぶべきか
この記事で紹介しようとしているのは、知識よりもより基礎的な部分で、本当に最初のプロジェクトー実際にコンサルタントとして採用され、トレーニングを受けアサインインタビューを経て、アサインが決まった方向けの内容です。
あるいは転職活動で実際に、コンサルティングファームを受ける上でどのような知識を得ておけばいいのかを確認しておきたいという方にも向いています。
2. 具体的なおすすめ-推薦図書-
具体的なおすすめ書籍を五つ記載します。
推薦図書として記載した書籍は、技術的な面、基礎知識的な面での底上げ、あるいは基礎的な土台の上にもう一段基礎を形作ることができる本です。
本当の基礎の基礎部分については、応用情報技術者試験の教科書を読むことをお勧めします。私は、僕は経営コンサルタントや戦略コンサルタントになるのであって、ITコンサルタントになるのではないという方もおられるかもしれません。
しかし、令和以降のビジネス環境にあってはITの基礎知識がなくコンサルタントをやっていくのは困難が伴います。
もちろん現在のコンサルティングファームのシニアマネージャー以上のクラスには深い業界やファンクション知識、コミュニケーションスキルなどを重視して、ITスキルは乏しく、下についたマネージャークラスや同格のシステムに強いシニアマネージャーで補完している方もまだまだ多いです。
しかしそれはある程度以上のクラスになったからこそできる技、コンサルティングファームの生き抜き方になります。
これからコンサルティングファームを目指す方がIT分野の基礎知識、デジタル分野の基礎知識を持っている事は決してマイナスにはなりません。
ここからはそんな前提を踏まえて、一言ずつ推薦図書へのコメントを記載していきます。
●コンサル一年目が学ぶこと
これは「コンサルタントとしての話す力」に一番寄与します。
新たにアサインされたコンサルタントが、コンサルタントとしての基礎的な事項を抑えているかいないかで、プロジェクトにおける日常的な会話が通じるか通じないかの分岐、つまりプロジェクトチームの空気がよくなるか悪くなるかが決まります。
具体的には業界の略語、社内の略語、はたまた業界や社内の前提知識をベースとした会話をプロジェクトチーム内では行っている為、用語の意味するところが理解できていないとそもそも話が通じないのです。
多くの場合、クラスが二つ離れるとこうした事態が起きやすいです。例えばアナリストとマネージャー、コンサルタントとシニアマネージャーやマネジングダイレクター(MD)などです。
それぞれのクラスによって見ているビューが異なる為、同じ会話をしていても用語の理解が追い付かず、かみ合わなくなります。
この書籍を読む際には、どういう点を注意すればよいのかという観点で読書することをお勧めします。
●考える技術 書く技術
これは「コンサルタントとしての書く力」に寄与します。
教科書や辞書的な存在として手元に置いた上で、折に触れて見返してみるという使い方が一番良いかもしれません。
あるいは数か月前など、時間を空けて自分の書いた文章と本書を照らし合わせて使うというのもありです。
この本は少なくともコンサルティングファームに入る段階では体得することは難しいですが、それでも推薦図書に入れているのはこういう考え方があるという考え自体に触れる体験をしていただきたいからです。
コンサルティングファームに入れば、自分自身よりもよほど深い示唆や洞察を、自分よりも短い時間で導き出せるコンサルタントがごろごろいます。そんな中でも自分自身の中で考えるフレームができていれば時間がかかろうと、一定の深さの示唆を導き出せる筈です。
本書で一歩一歩進んだ先に、少なくとも求められている深さの示唆は出せるのだという道筋の存在を学んでほしいと思います。
●外資系金融のExcel作成術: 表の見せ方&財務モデルの組み方
本書籍は「コンサルタントとしての書く力」「コンサルタントとしての調べる力」に寄与します。
コンサルタントとして駆使するフレームワークは様々ありますが、日常の業務で利用するしみじみとした型、フレームワークを学べる書籍です。
教科書に載っているようなフレームワークを使う機会ももちろんありますが、基本的に多くのタスクは何かを調べる、何かをまとめるということの繰り返しです。その繰り返しの中でバトル漫画のように自分自身がやらなければいけない、繰り出さなければいけない資料を「技」のような形で本書で覚えておきましょう。
実際にプロジェクトチーム内でこういうことを調べてほしいという話を受けた時点で、アウトプットの型(繰り出すべき技)が思い浮かばないようだったらもう少し本書を読み込んでみましょう。
●伝わるデザインの基本 増補改訂版 よい資料を作るためのレイアウトのルール
デザインは別にデザインコンサルタントやUXコンサルタントでなくとも重要です。各コンサルティングファーム内、あるいはそれぞれのシニアマネージャーやMDによって線の細さのルール、色身のルール(カラーパレット)、余白の生かし方のルールなど様々なバリエーションがあることでしょう。
BN(ブランニュー:新卒)や第二新卒のコンサルタントであっても、綺麗な資料と綺麗でない資料は見比べたらわかります。
本書は、何故きれいでないように感じるのかを分解して記載している書籍です。
もちろんひとつひとつは取り上げてみれば大したことは書いていないかもしれません。しかしその大したことのないことを当たり前のようにやれない若手コンサルタントがいるのも事実です。
上司から繰り返し矯正される前に、自分でキャッチアップして少なくとも汚いといわれない程度の綺麗さを演出できるようにしましょう。
●アフターデジタル
本書籍は「コンサルタントとしての話す力」「コンサルタントとしての描く力」「「コンサルタントとしての導く力」」に関係してきます。
クライアント企業の部長クラス以上ともなれば、過去のコンサルタント、コンサルティングファームとの付き合いや業界横断の勉強会、その他新規開拓しようとしてくるSaaS企業や別のコンサルティングファームの提案内容、営業資料によって様々な業界知識、IT知識、トレンドなどをある程度は抑えているものです。
現時点でどのようなトレンドがあり、どう変化していこうとするのか各コンサルティングファームがレポートなどを出していますが、それらも一応踏まえつつ、ガートナーなどのレポート、それからアフターデジタルなどの書籍を組み合わせて自分なりのビジョンを描いておくことが必要です。
そうしたビジョンのことをコンサルティング業界の用語ではビッグピクチャとも呼びますが、自分の中で未来の大きな絵図(ビッグピクチャ)がないと、タスク設計自体が場当たり的な対応になってしまい、かつクライアントと話す際にもその場限り、短期的な根拠づけに基づいた示唆だしなどをしてしまうリスクがあります。
もちろん自分自身が描いた絵図はクライアントの現実や、様々なアップデートによってどんどんんと変化させて言って構いません。エッジコンピューティング、フォグコンピューティング、IoT、スマートファクトリー、デジタルツイン、5G。世の中には様々なIT・デジタル分野のトレンドが存在し日々アップデートされています。
それらすべてを追いかけるのは難しいと思いますので、普段から何気ない会話などでプロジェクトチーム内でそれぞれが未来の絵図を描き、持ちよりちょっとしたディスカッションができるような空気感を保つきっかけにあなた自身が慣れるとコンサルタントとしても一歩抜きんでることができる可能性があります。
3. 読後の独学のすすめ
様々な書籍が存在してはいますが、なんだかんだで一番学びの場となるのは実際のプロジェクトの現場です。
コンサルティングファームはある種の福利厚生、あるいは研鑽の場の提供として過去のプロジェクト資料などは基本的に公開されていると思います。
公開されている資料について、まずは自分自身の携わっているプロジェクトと同じ業界、あるいは同じファンクションの事例を学びましょう。
それから、クレデンシャルリスト(PJのクライアント名と案件概要、規模感など)も内部向けには公開しているケースが多いので、そのリストを確認し興味のあるプロジェクトを毎週1本ずつ、自分なりに見るべき観点のリストを作ってみていくと半年後、一年後には大きな違いとなってくる筈です。
それではまたどこかで。
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
「最後の秘境 東京藝大」に出てくるような人物だったらコンサルティングファームでも大成するかもしれません。
何かを突き詰めて考えて考えた先の答えを探し続けるというプロセスは、芸術でもコンサルティングでも変わらないと思うからです。
美大生や藝大生にあこがれつつ、一般的な道を歩んでしまったものとしてはせいぜい、美意識を磨いたりしているわけですが、黒猫シリーズの教授やエルメロイ二世にはあこがれるものがあります。
最後の秘境 東京藝大―天才たちのカオスな日常:
おすすめ理由: ここに出てくる登場人物が身近にいたら、彼・彼女・その人たちの考え方、何を大切にしているかを聞いてみるといいかもしれません。
ハーバードの美意識を磨く授業:
おすすめ理由:普段の生活、あるいは自分の好きなブランドをなぜ好きなのか、考えるためのきっかけになるかもしれません。
黒猫シリーズ:
おすすめ理由:美学×ミステリという、うつくしさをテーマにしたミステリです。難しい本などは嫌だという方も、そういうのをテーマにした小説面白そうだねという方も不思議な世界へ旅立てるかもしれません。
ロード・エルメロイII世の事件簿:
おすすめ理由:魔術やFateシリーズが好きな方は、このスピンオフ作品漫画の4-5巻あたりが、黄金姫と白銀姫という人物にまつわる「美」というのが事件のテーマになっています。
それではまたどこかで。





